「古代ギリシャ人女性の服装」(さるHPより抜粋。Y・C・M)
[ 内衣と外衣]
古代ギリシアの衣服は、大きく内衣と外衣とに分けられる。前6世紀から前2世紀にかけて、最も標準的な内衣はキトン(chiton)であり、外衣は、キトンの上に着るヒマティオン(himation)である。
[ 内衣]
キトン(Chiton)は、貫頭衣の形式の寛裕(かんゆう)服で、長方形の一枚の布からなり、裁断しないのが特徴である。婦人用はくるぶしまであり、男子用はそれより短く、子供や軍人などのものはひぎまでであった(これを
キトニスコス(chitoniskos)と呼ぶが、まれに女性も着た)。下着をかねた普段着であったから、この下に何を着ていたのかなどと、無用な好奇心は起こさぬこと。(要するに下には何も着ていなかった ということだ!Y・C・M)。型はドリス式とイオニア式に種別される。
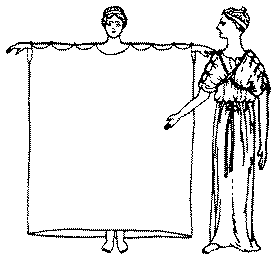
イオニア式キトンは、身体の両側を手の出る寸法だけ残して筒形に縫い合わせ、肩から手首にかけてたくさんの留め金でとめ、ウェストをベルトで締めるほかに、たすきのように肩からひもをかけたりする(上図)。
おもに白の麻織物で作られ、ドリス式に比べてひだが多く華やかである。
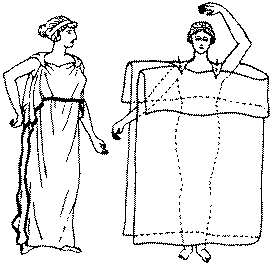
ドリス式キトンは、大きな四角い布地の上縁を1/5ほど表側に折り返し、さらに縦に二つ折りにして、かしわもち状に身体を包み(したがって、身体の右側は開いたままである! このことから、「隙間あるキトン(chiton
schistos)」とも呼ばれる)、両肩のところをブローチ(perone,
pl.peronai)で留めるほか、ウェストをベルト(これをゾーネー(zone)という)で締めたりして着用する(上図)。
おもに白の毛織物でできており、縁に線条の模様をあらわしたものもある。
ドリス式キトンの一変型と考えてよいのが、 ペプロス(peplos)であった。これは、ドリス式キトンの特徴である「隙間」を縫い込めただけのものであって、女神の立像によく見られる古い時代の着衣である。特に女神アテナのそれは有名で、オリュムポスの神々と巨人族との戦闘と勝利の模様が、一面に刺繍してあったという(プラトン『エウテュプロン』6C)。
時代から言うと、ドリス式の方が古く、イオニア式は比較的新しい(前6世紀の初めころ)。明らかに小アジアの影響がうかがえ、アテナイを中心に着用されるようになった。しかし、ペリクレスの時代には、男性がイオニア式キトンを着ることはなくなり、もっぱら女性用着衣となった。
ドリス式からイオニア式への転換について、ヘロドトスが妙な話を伝えている。
アテナイがアルゴス、アイギナを攻めたとき、アテナイ軍は1兵を除いてことごとく戦死した。生き残ったその兵士がアテナイに帰って悲報を告げたところ、女たちはこの男ひとりが生き残って帰ったことに憤り、その男を取り囲み、ひとりひとりが着衣の留め針でその男を刺し殺してしまった。アテナイ人たちは、敗戦の悲報よりも、この女たちの所行に恐れをなし、以後、女たちの衣装を、留め針のないイオニア風に改めたというのである(『歴史』第5巻87。なお、留め針の持つ神話的意味については、反・ギリシア神話の 「オイディプス(oidipus)」の項を参照されたい)。
しかしスパルタでは、女性もドリス式キトンの古風を守り続けていた。
[ 外衣]
家の中では、普段は内衣であるキトン一枚で過ごした(だからブラジャーだのパンテイーだの、あるいはガーターだのという野蛮なしろものは、かれら古代の女性たちの夢にも知らない衣料品であった。Y・C・M)が、外出するときなどは、キトンの上に ヒマティオン(himation)と呼ばれる外衣を着用した。ヒマティオンは、「衣服」を表すヘイマ(heima)という語から転じたもので、本来は巻衣型の外衣一般をさす名称であった。いずれもウール地の方形である点では一致しているが、大きさや着方は一定しない。
パロス(pharos) ホメロスでは、おもに男性が着用したが、女性も持っていた(『オデュッセイア』第5巻230、第10巻543)。屍体に打ちかける帷子としても(『イリアス』第18巻353、第24巻580)、寝台の上掛としても(ソポクレス『トラキスの女たち』916)用いられた。オデュッセウスの貞淑な妻ペーネロペーが、しつこい求婚者たちへの返事を引き延ばすために織り続けたのも、pharosであった。
しかし、この語が出現するのは叙事詩と悲劇のみである。例外は、ヘロドトス『歴史』に2箇所(第2巻122章、第9巻109章)だけで、普通、散文ではヒマティオンの語が用いられる。
クライナ(chlaina) ホメロスでは男性のみが着用したようであるが、これもまた夜着としても使われ、パロス(pharos)とも次のヒマティオン(himation)とも呼ばれ、その区別は必ずしも明瞭ではない。しかし、ヒマティオンと区別するときは、ヒマティオンよりは厚手で温かい防風・防寒着として用いられた(例えば、『イリアス』第16巻224、『オデュッセイア』第14巻529)。しかし、山羊の毛の外衣である シシュラ(sisyra)よりは薄手である。また、目の粗い トリボーン(tribon)のような安物ではなく、高価なため、褒美として与えられることもあった(『イリアス』第24巻230、ヘロドトス『歴史』第2巻91)。
通常、 ヒマティオン(himation)といえば、多くは縦1〜2m、横3〜5.5m程度で、女性が頭からフード状にかぶる、男性が身体の脇の直下から巻きつけるなどの着方があった。色は白・緋・紫などで、縁模様などをほどこしたものもある。
いずれも夜着としても、屍体を覆う帷子(かたびら)としても用いられた(屍体を覆う場合は、3枚のヒマティオンが用いられた)。
夜着というと、布団を身にまとっていたような印象を受けるかも知れないが、日本の中古においても、男女が情を交わすときは、それぞれが着ている衣を脱いで、これを掛けて同衾する。翌朝は、それぞれが掛けた自分の衣を着て、男はなごり惜しげに帰る。これを「衣々(後朝とも書く)の別れ」というのである。 (「みよしのの山下風の寒けくにはたや今宵も一人寝るらむ」・万葉集より。「きりぎりす鳴くや霜夜の寒けさに衣方敷き一人かも寝む」・百人一首より。どちらも同衾(ドウキン=抱き合って寝ること)する相手がいない寂しさを痛切に表わしている。とくに前者は持統女帝サーラの絶唱ともいうべき名歌。Y・C・M。)。
アルキビアデスがソクラテスを誘惑して、自分の外套をソクラテスのぼろ外套におっかぶせて同衾したとき(プラトン『酒宴』219b)、ソクラテスのぼろ外套がtribon、アルキビアデスの外套がすなわちhimationであった。
クラミュス(chlamys) ヒマティオンよりも短くて小さい外衣がこれで、身体に斜めに羽織って、右肩のところでブローチで留めた。実用性よりは装飾性の意味合いが強く、若者や騎兵などが着用した(壺絵では、ヘルメス神が着用。右図)。
男と同様に女性も着用したのが、 クラニス(chlanis)であり、これの縮小語
クラニディオン(chlanidion)はもっぱら女性が着用した。
古代ギリシア女性の衣服については、 J.
Moyr Smith's Greek Female Costumeが必見。キトン、ヒマティオンがいかに優雅な衣服であるか、十二分に堪能させてくれる。
→「時代考証のページ」へ戻る